町中をドリブルするサッカー少年
サッカーを始めた幼少期の記憶の中で、鮮明に覚えていることがいくつかあるという。
6歳年上の兄がかつて入っていたクラブに親に連れていかれた、その初日のこと。
「体育館で大きいボールでバレーボールのようなことをやって、それから外に出てサッカーをしたことを、鮮明に覚えています」
その後、人数減少などで続けられず、次に入ったクラブは最終学年が3年生までだったため1年間の所属で終わってからは、半年ほどは、ひとりでサッカーをやっている時間もあった。学校から帰ってランドセルを勢いよく置いたら、町中を壁当てしながらドリブルしていく車屋少年。
「バンバン当てまくってたけど(笑)、田舎だったから許されたんでしょうね」
ある時、家が近所だった谷口彰悟も入っていた熊本ユナイテッドの練習に参加したが、「当時から人見知りだった」車屋は一度行ったきり、またひとりで練習するようになったという。
小学4年のある日のこと、「学校の廊下で彰悟さんから『監督がまた来いって言ってるよ』と言われて、『じゃあ行くか』と」熊本ユナイテッドに正式加入。
「今思えば、彰悟さんから声をかけられなかったら、入っていなかったと思います」
それから、毎日のように1歳上の谷口彰悟も含めた3人ほどに、ひとり年下の車屋が混ざって、一緒に行動するようになった。
「僕の方が先に授業が終わるから、彰悟さんの教室前の廊下で待っていて(笑)、毎日のように遊戯王をやったり、練習に行ったり、サッカーをしたりしました」
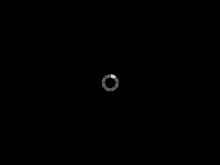
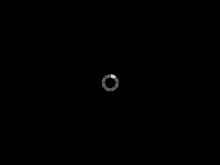
自分に満足できず練習していた
「いつも彰悟さんの代は強くて、僕の代はそうでもなかった。でも僕は勝ちたかったから周囲と温度差が正直あったと思う」
中学時代は部活動でサッカーをしたが、3年生最後の中体連は市内で1回戦敗退と、なかなかチームの結果は出なかった。それでも、小学生の頃と変わらず、流されることなく、時にはひとりでも練習を続けた。
「相変わらず町中にドリブルしに行ったり、塾から帰ってきてから公園でボールを蹴ったり、夜遅くまで練習することもありました。ひとりで練習するのは心細かったこともありますが、 周りから強制されたわけでもないし、 親から練習するように言われたわけでもなかったのに、とにかく練習ばかりしていました。それは、サッカーが好きでうまくなりたいという思いだけでした。今でも覚えているのが、僕が空き地でひとりで練習していたら、友だちがチャリで通りがかって『お前、何でやってるの?』って言われたこと。その表情とか言い方とか、すごい引いていたので(笑)覚えています。
僕は、ずっと自分に満足できなかった。大会でも勝ててないし、自分がうまいとかすごいと思ったことも一度もなかったから、その分練習しなきゃとずっと思っていました。
振り返ってみると、純粋に楽しいだけでサッカーをしていたのは小学3年生ぐらいまでで、4年生ぐらいからは、すごく考えて練習するようになったし、何気なく適当にやる時間がなかった。練習がうまくいかなかったら、学校でもサッカーのことをずっと考えていました。たぶん、どこかで自分を許せない性格なんです。結局、サッカーがうまくなりたい気持ちが強すぎて、苦しい時間も長かったような気がします。ドリブルしていた時も、楽しさの中にも、どこかでうまくならなきゃいけないという自分の気持ちに縛られてやっていたところもあったのかな。でも、そうやって考えて練習をし続けたから、今(プロ)に絶対つながっていると思います」
3年間無遅刻・無欠席の大津高校時代
高校は強いところでサッカーがしたいと、強豪の大津高等学校に入学。
環境的にもサッカー漬けの生活が始まった。
本人いわく、「トレセンに入ったりはしたけど、無名の中学生」と認識していた車屋だったが、恩師の平岡和徳の鑑識眼により1年生からトップチームに抜擢された。
「入った時は、自分は強い選手たちについていくと思っていたので、1年の時は『何で俺なんだ?』ってずっと思っていました。平岡先生の長年の経験からくるものなんでしょうけど、いまだに理由がわかりません(笑)。でも、先生は、僕だけじゃなく、小学生時代にエリートで中学時代は伸び悩んだ時期もあったと本人から聞いたことがあった彰悟さんも植田(直通)もそう(1年で抜擢)だったと聞きました。先生は6時からの自主練にも必ず時間前にグラウンドに出ていたし、それを毎日当たり前のようにやり続けることってなかなかできないことだと思います」
谷口が3年生で主将、車屋が2年時の選手権熊本県予選決勝では、谷口がその後も「サッカー人生の挫折であり、心底悔しかった。僕は今でももう一回やったら勝てると思っている」と語ったルーテル学院戦で無念の敗戦。夏のインターハイで全国ベスト4になり、自信がある状態で迎えながら、スーパーシード校として準決勝からの出場となり、リズムを掴みにくかった要素もあっただろう。車屋は「本当に一発勝負は難しいと感じました」と振り返る。
「僕たちが3年生の代は、新人戦も総体も負けて、一回も県内を獲れないままで、そこから平岡先生が運転して大阪まで遠征に行ったり、本当にそういう先生の姿勢はすごかった」
県予選決勝では、再びルーテル学院戦となり、延長戦を制して、最後は車屋が必死のクリアをして全国へ。選手権は1回戦敗退に終わった。
「高校時代は4時30分に起きて5時に出て、熊本なのでそんなに駅数もないから、チャリで駅まで20分、朝5時からそんなに飛ばすかっていうスピードで(笑)、電車でさらに30分。1年生は電車内で立っていたので、足もパンパンになる。チャリも行きは下りだけど帰りは上りだから大変で、足腰鍛えられました。本当に3年間はめちゃくちゃ練習したし、きつかったけど、課題を自分で見つけて練習するのが当たり前の環境だったから、より自分に足りないことは何か考えて取り組むようになったと思います。本来は午後練習後は早く帰宅して翌朝の自主練に備えないといけないところを、体育館裏とかで隠れて練習していたこともありました。
僕は、3年間学校も無遅刻無欠席だったし、風邪を引いた記憶もない。多少痛いのぐらい言ってられないというか、ケガもしなかったし、よくやったなと思います」
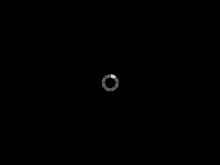
筑波で“風間サッカー”に出会う
スムーズに大津高校から筑波大学に進学したように経歴だけを見ると感じるが、「いやいや、全然そうじゃなかった」と車屋は振り返る。
「両親からは私立は難しいと言われていたので、最初は九州で鹿屋体育大学や福岡教育大学への進学を考えていました。そもそも筑波に入れるのはエリートだけだと僕も両親も思っていたところ、相談した平岡先生から『プロを目指すなら筑波がいいんじゃないか』と言われ、先生の母校でもある筑波にスポーツ推薦枠で受験することになりました。とはいえ、5人枠だし、時期もかなり遅く、もしダメだったら就職するしかないとも思っていました。もし不合格だったら、今頃どうなっていたんだろう…と思います」
そして、大学1年でサッカー観が合い、影響を受けた風間八宏の指導を受けた。
「まだ熊本にはJリーグがない小学生の頃、ジローラモさんが出ていたセリエAダイジェストを観て、友だちとアドリアーノやビエリのことを『すごいね』と地元では珍しい会話をする小学生だったと思います。その後は、風間さんが出ていたマンデーフットボールを観ていました。中学生の頃に好きだったのは、ロナウジーニョで、特集を録画したビデオは、本当に擦り切れて映らなくなるまで観まくりました。当時、スペインリーグの中継はWOWOWしかやってなかったので、親にどうにか頼み込んで契約してもらって、部活が終わって家でバルセロナの試合をしょっちゅう観ていました。ロナウジーニョ、若い頃のメッシもいて、バルセロナを応援していました。
子どもの頃から漠然と考えていた理想に出会ったのが、ボールを保持して攻めるバルセロナのサッカーで、高校生の時には、EURO2008があり、スペイン代表の攻撃的サッカーが好きで、彰悟さんからDVDを借りてめちゃくちゃ観ていました。そういう自分のサッカー観を落とし込む人に出会ったのが風間(八宏)さん。大学1年の1年間、今までで一番成長したと実感したので、そのスタイルで勝ちたいとフロンターレに加入する一番の理由にもなりました。時代も人も変わっていく中で難しい部分も出てくるかもしれないけど、それがフロンターレが続けてきたサッカーのスタイルだと思うし、知っている選手たちが続けてほしいなと思います」
車屋は大学1年の時に新人賞、3年生の時にユニバーシアード代表として銅メダル獲得、ベストイレブン受賞。膝のケガで離脱した時期以外は、4年間を通じて試合に出続け、関東大学リーグ最多出場を仲川輝人ら4選手と共に受賞した。そして、背番号7をつけた4年の時には、引き分け以上で1部残留が決まる状況で迎えた最終節、アディショナルタイムに逆転弾を喫して、筑波大学史上初の2部降格という悔しさも味わった。
「大学時代も上の世代は強くて、僕より下の世代がなかなか試合経験を積めていなかったなか、なんとかしなきゃという責任も感じていました。今思うと、当時もけっこう追い込まれていたかもしれないですね。大学時代も、周りからは『すごい』と言ってもらうこともありましたが、自分に対してそう思うことが一度もなかったし、常に自分を追い込んでいたように思います。だから、辛かったですが、でも、プロになった人は、そういう想いを人が見てないところでたくさんしてきているんだろうなと僕は思います」
1本の電話で大学4年で試合デビュー
風間八宏の存在が、フロンターレ加入の決め手だった車屋だが、ファーストフロンターレはもっと遡る。
「小学生から中学生の頃、ウイイレでなぜかフロンターレを使っていました(笑)。強かったし、かっこいいなと思って使っていたんじゃないですかね。大学になり先輩たちがプロ選手になり、自分もめざすようになると、Jリーグの試合をよく観るようになりました。プレーの質もそうだし、技術も高いし、ミスも少ない。たくさんのお客さんの前でプレーすることもそうだし、やっぱりすごいんだなと気づきました」
特別指定選手となっていた大学4年の時、大学のリーグ最終節が11月15日に終わり、11月22日第32節鹿島アントラーズ戦(アウェイ)の試合を観戦に行った翌日、知らない番号から連絡があった。
「出たら風間さんで、急きょ寮に泊まり練習に参加することになりました。卒論もギリギリに差し掛かっていた時期だったのですが(笑)。それで、次のホーム広島戦と最終戦のアウェイ神戸戦で試合に出ることになりました。広島戦は、もちろん緊張したし、アップの流れもわからないから、彰悟さんに声をかけてもらって。驚いたのは、スタンドから観戦していた景色と、等々力のピッチから観たサポーターを含めたスタジアムの光景がまったく違ったこと。『こんなにお客さんがいるんだ。すごいな』と感じたことは今でも覚えています。当時は必死で考える余裕もなかったですけど、いきなり大学生が試合に出てきて、他の選手やサポーターはいろいろ思うこともあったでしょうね(笑)」
実際は、周囲からはワクワクする期待感で迎えられ、翌2015年、新人選手として伊藤宏樹以来の開幕スタメンを飾った。本人は、プロ初年度は、レベルの高さに驚きが大きかったという。
「とんでもないところに来ちゃったなと衝撃が大きかったし、実際にテレビで観ていた選手たちがたくさんいる環境にも緊張しました。大学ではパワーとスピードで負けると思ったことがなかったので、やれていた分レベルの高さにギャップを感じたし、そういう中で、大卒1年目から結果を出さなきゃいけないと思っていました」
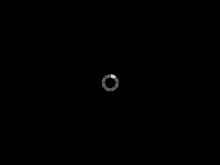
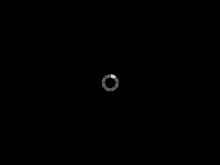
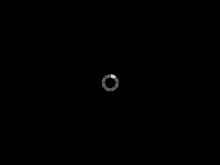
挑戦し続け、掴んだ初優勝
ここでも本人の実感とは別に、1年目からリーグ戦に30試合に出場すると、そのまま左サイドバックの主力選手として定着した。
「最初の頃はどちらかというと左サイドは中に入ってプレーする選手が多かったので、中野(嘉大)、三好(康児)、橋本晃司さん、阿部ちゃん(浩之)もそうですが、自分がサイドを駆けあがってタイミングよく裏に抜けたり、そういう僕の特徴を分かって活かしてやってくれたなと思います。仕掛ける時には、彰悟さんとかセンターバックの選手が足元にシンプルにつけてくれたり、ケンゴさんとか僕のスピードを分かって出してくれていたし、すごく活かしてもらったなと思います。
インパクトがあった2015年を経て、プロキャリアの中で2016年が一番パフォーマンスがよかったと実感しているという。
「2015年は自分の足りない箇所を練習前にトレーナーさんと一緒にトレーニングしたり、いろいろ取り組んでスピードにもだんだん慣れてきて、2016年は開幕から1年間ずっと調子がよかった。自分のサイドからかなり崩せる手応えがありました。だから、2017年と2018年にベストイレブンを頂きましたけど、自分のなかでは2016年が一番よかったと思っています」
タイトルがまだ獲れていないフロンターレが初めて優勝する、その歴史の一員として挑戦したいということもチームを選んだ理由のひとつ。2017年には、日本代表でも初キャップを記録し、元日の天皇杯決勝、ルヴァンカップ決勝の悔しさも味わい、仲間と掴んだ初優勝だった。
「今思うと、あの年はめちゃくちゃ全員濃かったですよね(笑)。それはすごい感じます。オニさんが監督になって、よりチームが新しくなった感じがしたし、最初こそ苦戦したけど、本当にちょっとずつ、ちょっとずつチームが成長している感じがあったし、一体感が徐々にできあがった」
負けられない状況で迎えた10月の雨の日立台での柏戦、家長からボールを受け、ピッチコンディションを感じさせない美しいクロスを含めた2アシストでチームに貴重な勝点1をもたらした。
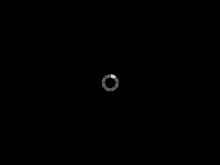
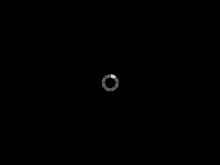
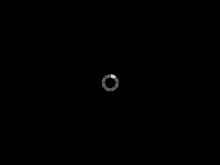
「最終節の大宮戦なんて、本当にチームがひとつになっていたと思うし、集大成だったなと思います。
僕は、試合が終わった瞬間はピッチの真ん中辺りにいて、アキくん、ケンタロウくんとかと話をしていて、まだ実感がなくて、オーロラビジョンに鹿島の試合結果が映し出された時、優勝したんだってやっと感じられました。
あの年は、僕たち世代もベテラン選手に頼ってちゃダメだと思っていたし、いずれそういう先輩たちがいなくなることも覚悟しないといけないという危機感も持ってやっていました。
2連覇した2018年も強かったけど、なんというか、2017年の方が、“トゲ”というか、激しさがあったのかな(笑)。2018年の方が落ち着いていたかもしれないですね」
2017年は、リーグ戦34試合全てでスタメン出場し、連戦で戦っていたACL10試合を含めて、カップ戦、天皇杯、さらには日本代表での2試合出場もあり、フロンターレの公式戦のほとんどに出場するというフル稼働なシーズンだった。
「僕だけ休憩なしみたいな時もありましたね(笑)。いろんな大会があって連戦も続いたけど、なんとなく『紳太郎は、いけるだろう』っていう感じがあって。やるしかないと思ってやってました。サイドバックほどには走らなくていい分、センターバックで出る時には、それがちょっとだけ休憩みたいな感じでした(笑)」
切磋琢磨
登里享平とのポジション争いが、プロ選手同士の緊張感がありながら美しいとすら感じる競争に見えたのは、それぞれがチームが勝つために何をすべきか考えて振舞いながら、自分自身と向き合い、変化もさせながら、自分の良さを発揮して、互いを認めながら切磋琢磨できるふたりだったからだろう。
「2018年までは左サイドバックで僕がスタメンで、2019年からはノボリくんも出るようになって、僕も入れ替わりながら出て、2020年開幕からは基本的にノボリくんが左サイドでファーストチョイスで出るようになりました。僕自身のことを言えば、ちょうど2020シーズンまでの契約期間だったので、覚悟して臨んだ年だったし、活躍できなければ、選手として環境を変えることも視野に入れて考える必要も、チームからもそういう判断になる可能性もあるだろうと考えていました」
そういう中でホーム等々力で優勝を決めたガンバ大阪戦のこと。
「ラスト1プレーでコーナーキックをクリアして終わったその直前、僕はボールがないところにいて膝が急に過伸展したんです。その瞬間、半年ぐらいのケガになるんじゃないかと思い、これがフロンターレでの最後の試合になるかもしれないと思いました」
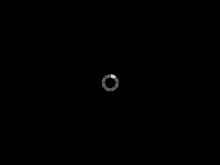
ケガの全治もわからない状態で臨んだ面談の場で、クラブから必要とされたことは、「自分は愛されているんだな。最後までフロンターレでやりたい」と考える大きな要因になった。
「結果的にそのケガはそこまで長期間かからないと後日わかったのですが、プロとしてセンターバックとしても勝負してみたかったという気持ちも受け止めてもらい、感謝しています。今から振り返ると、2020年ぐらいまでは自分のためにやっていた面も強かったし、もう一度自分がスタメンを勝ち取るんだ、取り返そうという思いもありました。それを経て、2020年末の出来事があって、フロントともオニさんとも話をして、スタメンでも途中出場でもチームから必要だと言われたら100%で尽くそうと、チームに対する見方も変わったと思います」
登里とのポジション争いや、センターバックでの新たな挑戦についても、こう振り返った。
「ノボリくんから見たら、僕が2015年から出始めて2018年まで出ていたから、きっと辛い思いもしていたと思うし、本当にお互い切磋琢磨してやってこられたのかなと思います。
その後、僕がセンターバックで挑戦してからは、センターバックでは彰悟さんがファーストチョイスだったので、いかにスタメンをもう一度取りに行くか、ということはすごく意識していたし、途中出場でも自分のアピールになると思って取り組んでいました。
大学時代にもやっていたセンターバックをプロでやってみたいという僕の気持ちをオニさんも聞いてくれて、まぁその後もサイドバックで出ることもあって、2021年は半々ぐらいだったんじゃないかと思うけど(笑)。でも、必要とされたらやるしかないですよね。
実際、ひとつのポジションですべてを出すのとまた違った意味で、センターバックとサイドバック、どちらで出るか分からない時はけっこう難しいんですよ。ベンチからも両方の動きを見ておいて、起きている現象、相手選手、自分が想定すること、その両方を準備するので、そこは大変でしたね。
2021年、2022年の2年間は、常にスタメンというわけではなかったし、途中出場することも多かったけど、自分の手応えもあったし、いいプレーも出せたと思う。2021年は優勝に貢献できたと感じられたし、2022年は残念ながら2位でしたけど、やれたと自分で思えました」
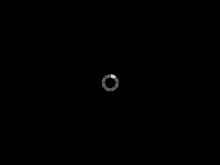
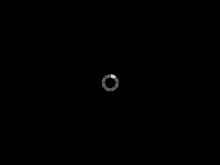
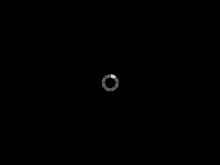
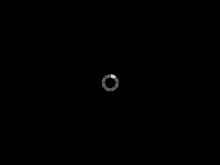
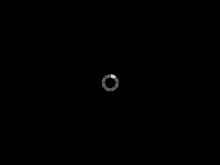
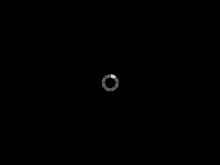
ディフェンスリーダー
2023年は、谷口彰悟が海外移籍で抜けた後、自他ともに「自分がディフェンスリーダーとして引っ張るんだ」という覚悟を持って臨んだシーズンだった。
ポジションから生まれる選手としての役割や、チームメイトを引っ張る立場である自覚もあった。
「センターバックにポジションが変わったことで、自分自身にも変化がありました。20代後半までサイドバックをやっていた時は、使われることの方が多かったから、自分自身に集中してやっていました。
センターバックは、声を出したり周りを動かすことが大事になるので、意識がより変わったし、そういう経験を自分がプロに入ってからしてきていなかったので、難しさを最初はすごく感じました。
センターバックはポジション自体がディフェンスリーダーだし、セットプレーも含めてラインコントロールをするし、より責任感が自分の中で生まれて、実際すごくやることが多いポジションだと感じます。攻撃でもビルドアップのスタートになるし、ディフェンス面でもそれまでは自分が上がって後ろに任せていたことが、よりやらなきゃいけないことが増えて、サイドバックの時には気づけなかった大変さがありました。その分、より頭を使うし、周りを動かすことも必要になりました。
もちろん声掛けはすごく大事だし、間違ってもいいから、なるべくしゃべる。間違ったら修正すればいい。まずは声を出すところが大事かなと思います」
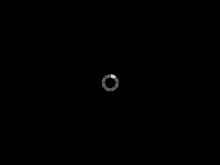
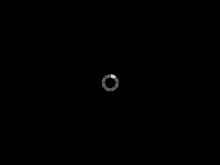
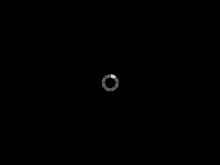
2023年7月15日、J1第21節横浜F・マリノス戦で、後半アディショナルタイムに、ディフェンダーとしての万が一のリスクを理解しながらも車屋がゴール前に詰めて決勝ゴールを体ごと押し込んだのは、「このチームを自分が勝たせるんだ」という強い意志からくる行動に感じられた。
当時、こんなことを話していた。
「彰悟さんが抜けて年齢的にも自分がディフェンスラインを引っ張っていくという気持ちが必要になると思っていましたし、とくに真ん中でプレーするので、(高井)幸大や(大南)拓磨と組んだときに、自分がみせなきゃいけないというのは感じてきました。ディフェンスラインは4人のラインコントロールを合わせる声がとくに必要なので、練習からもよく話しますね。幸大とは年齢差はありますけど、それは関係なく(センターバックのパートナーとして)僕は見ていますし、お互いに思ったことは言い合えていると思うので、そういう関係は大事にして僕自身も壁を作らないようにしています。
センターバックは、後ろにいて、この選手がいれば安心できるという安定感をチームにもたらしたり、それは守備だけじゃなく、攻撃の部分でも、この選手がいたら安定感があるという選手が必要なんじゃないかと思います。
僕は、後ろに限らずどのポジションでも、そのポジションなりの大変さがあると思っています。もちろんセンターバックは失点に絡めば、映像に出て、言われることもあるし、難しいところはあります。その回数を減らしていくことは大事ですけど、試合を重ねながら、徐々に気を付けなければいけないことは学んでいくものだし、でも、学んでも0にすることはできない。そうなったときに、もちろん反省はしなくてはいけないですけど、人間なので、また同じミスをするかもしれない。それは、サッカー選手に限らず、どの仕事でもそうだと思うし、どんなに集中していても起こってしまうことはあるので、反省は大事ですけど、引きずりすぎるのはよくないし、それで積極的なプレーができないとそれはそれでよくないし、そこはバランスが難しいところではあります。僕自身は、引きずることも引きずらないこともありますけど、選手は1試合で評価がガラっと変わるものだと思うので、たとえよくなくても引きずる必要はないと思うし、次の試合でまた頑張ればいいだけ。逆にいいときほど、調子に乗りすぎない。そういうバランスが大事かなと思います。ただ、切り替えられることは、選手として一番大事なメンタルなんじゃないかなと思います」
決断
2023年9月、湘南戦で膝を負傷してからは、痛みがなかなか取れない時期もあり、2024年1月に手術を経てからも、長く費やすことになったリハビリ期間の間は、苦しい時間が続いた。
「左足でボールが蹴れないぐらいに痛みがある時期もあって、右足だけで練習したこともありました。恐怖心もなかなか取れなかった頃は、このままだとサッカーもそうだし、子どもたちと一緒にボールが蹴れなくなるんじゃないか、と気持ちの面でも苦しかったし辛い時期もありました。今シーズンに関しては、膝の痛みが取れていた中で、何度か筋肉系のケガがありました。やっぱりケガのところでは、気持ちの面でも難しい時間が長かったです。そういう時期はあまり人にも会いたくなかったし、リハビリの時間を少しずらしてもらったこともありました。PT(フィジオセラピスト)の工藤さんとは、ずっと一緒にいたので、たくさん会話をしていました。
引退するという意志をクラブに伝えてからは、お世話になった方たちに連絡をしたり、熊本や筑波にも挨拶に行きました。長くやってきた選手やスタッフには自分の口から伝えて、リリース前にはチームメイト、スタッフの前で挨拶させてもらいました」
フロンターレの車屋紳太郎として現役を終えるという選択も、まだフロンターレの選手としてプレーが続けられる状況下で自ら幕を引いた決断も、周囲の人たちから「まだまだできる」と言われながらも、自らの「信念」を貫いた。本人の考え方によるものや心の葛藤も当然あったなかで決めたことであり、労いと感謝の気持ちを持って受け止めたいと思う。
“戦闘民族”な先輩たち
引退のリリースが出た時に、「公式戦で340試合(その後、ホーム最終戦に出場し341試合)に出ていたのか。そんなに出たのかって今思うと感じます」と話していた車屋。
自身のサッカー人生を振り返りながら話をしていた中で、自分のこと以上に熱量を持って話していたのが、“お手本となる先輩たち”についてのことだった。
「引退を伝えてからアキくんには『俺はまだ認めてへん』ってずっと言われてましたけど(笑)、アキくんは、僕がリハビリ中にあんまり人目がつかないように行動していたのがバレていて、気を遣ってくれて会ったら『おい!』って絡んで話しかけてくれていました。本当にお兄ちゃんって感じで優しいんですよ。24、25歳の若い頃からよくごはんにも連れていってもらって、めっちゃよくしてもらったし、面倒みてもらったなと思います。上の先輩の中では、一番しゃべる人かな。
本当にアキくんも悠くんもソンリョンさんも、ああやって長くこのチームにいる選手たちには、本当にお世話になりました。ソンリョンさんは、本当に優しくて、ご飯にも行かせてもらったし、気を遣わないように接してくれてめちゃくちゃしゃべりやすかったです。
先輩たちは、本当のプロフェッショナルだし、能力で見せることもそうだけど、姿勢とか、ピッチ内外で本当にあの人たちがいてくれてよかったなって心から思います。まず、あれだけ続けられるってことは、力がないとやれないことで、能力がずば抜けてすごい。ずっと、サッカーにすべてを捧げている。本当に選手って気持ちをコントロールするとか難しい面があるんですけど、あの人たちは、なんかもう、“戦闘民族”なんです(笑)。
戦うところをいまだに持ち続けていることはとんでもないことだと思うし、フロンターレだけじゃなく他のチームの選手からもめちゃくちゃリスペクトされていると思うし、ああいう選手たちを見てフロンターレの選手たちが育ってきたから、本当にいいお手本がいるなと思います。
オニさんの最後の試合も、スタンドから観ていて、震えましたから。もう役者が違うんです。ソンさんもすごかったし、ああいう試合でアキくんと悠くんがちゃんと点を取る。悠くんのこぼれ球に詰めていたのは、普通はGKが軽々キャッチするシーンのように見えたけど、『それ行くんだ』ってそれでも詰めている。ふたりのゴールには、鳥肌が立ったし、『すげぇ』と思いました。本当にサッカーに対する想いとかコツコツ培ってきたものとか、あれは真似できないなと思います」



























































