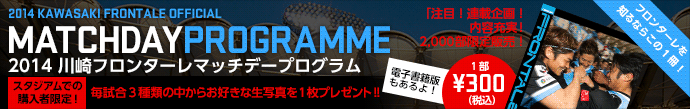Site Searchby Google Search
F-SPOTKAWASAKI FRONTALE FAN ZONE
創立20周年を迎えたクラブの歴史のなかで、14年目と最長の在籍年数を誇る中村憲剛。
プロとしてのキャリアをフロンターレでスタートさせ、同じ成長曲線を描きながらともに歩みを進めてきた。
世間からはベテランと呼ばれる域に入っているが、サッカーへの熱意はもちろん、
自分を育ててくれたクラブへの思いは誰にも負けないという自負がある。

「20年前?16歳になる歳だから高校1年生かぁ。当時は身長が154センチしかなくて、体もめちゃくちゃ細かった。ベンチプレスのバーを上げるのも必死だったもん。あれから20年。長いね、長いよ。ヒロキさん(伊藤宏樹・現強化部)が現役で13年やったのかな。下部組織からいる三好(三好康児)や板倉(板倉滉)でも10年ぐらいでしょ。俺もだいぶ変わりましたね。もともと末っ子キャラだったはずなんだけど、いつの間にか長男になっちゃった」
「20年前、何してた?」と憲剛に質問すると、こんな答えが返ってきた。
1997年といえば、Jリーグブームがひと段落した頃。いまと比べて情報を入手する手段が限られており、高校サッカーに打ち込んでいた憲剛にとってプロは遠い世界だったという。
「ただ変わっていないのは、サッカーが好きということと、うまくなりたいっていう気持ち。それがないとここまで続けられないでしょう」
フロンターレは2000年にJ1に昇格したが、1年でのJ2降格を経験している。その後、2001年途中から監督に就任した石崎信弘氏(現山形監督)のもとで、チームは着実に地力をつけていった。
「石さん(石崎監督)が来て3年目の2003年に俺がフロンターレに入って、1年目はあと一歩のところで昇格を逃したけど、その次の年にぶっちぎりで優勝した。それが12年前。思い出してみるとそんなに昔と感じないんだけど、1年を重ねていくといつの間にか遠くなっていくんですよね」
2004年、石崎監督からバトンを受ける形で関塚隆氏(現千葉監督)が監督に就任。圧倒的な攻撃力で勝点を積み重ねて断トツでJ2優勝を果たすと、二度目のJ1昇格からとんとん拍子で優勝争いに絡み初のACL出場権を手に入れるなど、観客動員数を含めてクラブは右肩上がりで成長を続けていった。
「地域の人たちも巻き込んで、いまじゃ観客動員2万人は当たり前ですからね。忘れもしないですよ、2003年のホーム開幕戦。湘南との試合で、そのときの観客が3千人でしたから。くしくも今年、第1節、第2節が2003年と同じカードなんですよ。知ってました? シーズン開幕戦がアウェイ広島戦で、それからホーム開幕戦が湘南戦。何か因縁めいたものを感じますね」
J1で安定した成績を残しクラブの知名度が上がるとともに、他クラブと競合するような将来有望な新人がフロンターレを選ぶようになり、代表を経験したビッグネームが加入するようになった。クラブ創立当初は地元川崎でも認知度は低かったが、いまではサッカーに興味がなくても川崎フロンターレの名前は知っているという人が多くなった。
「そこは成績を残すことで代表選手が出たり、得点王が出たりすることはありますけど、クラブとしてのヴィジョンがしっかりしていて、その地盤を固めてきたからだと思います。
あとはやっぱりサポーターでしょう。考えてみてくださいよ。フロンターレができた年に産まれた子どもがもう二十歳ですからね。親と一緒にスタジアムに来てた子どもが、いまではお父さん、お母さんになってるかもしれない。やっと世代がつながっていく長さになってきたんじゃないですか。ヨーロッパみたいにクラブが100年続くと、おじいちゃん、ひいおじいちゃんの世界ですからね。そういった伝統や文化を日本で作るのは簡単じゃないかもしれないけど、川崎に根づいてひとつの娯楽になりつつあるのは純粋にすごいことだと思います」
クラブを取り巻く環境面では、2007年に練習グラウンドのピッチが拡張され、2010年には独身寮が建てられた。2012年の終わりから改修が進んでいたメインスタンドが2015年に完成し、今年からはクラブハウスも新しくなった。環境面だけでいえばJリーグのビッグクラブと呼ばれるチームに匹敵するだけの設備が整ってきた。
「あと足りないのはタイトルだけ。もちろん昔のクラブハウスも味があったけど、環境が人を成長させると思うし、選手のモチベーションも上がる。だって、あんなすごいクラブハウスができて、ここまで環境を整えてもらったんだから、俺たちがやらないわけにはいかないでしょう」





憲剛自身はチームがJ1に昇格してからレギュラーの座をつかみ取り、日本代表にも選出され、クラブと代表のかけ持ちという過密日程のなかでコンディションやモチベーションを維持していくための方法を学んだ。もちろん若さゆえの勢いだけで突っ走った時期もあっただろうが、試合に出続けるのが当たり前という状況で経験を積み、中村憲剛に求められる役割、そして周りからの目も日に日に高いものになっていった。そんな重圧のなかで心の拠り所になっていたのは、家族の存在だった。
「今思えばいい思い出しかないけど、家族には迷惑をかけました。子どもが生まれたばかりの頃は1年の半分ぐらい家にいなかったですから。『あのとき本当に家にいなかったよねえ』って、いまだに妻に言われますけど…。昔のホームビデオをたまに見るんですけど、そこに自分がいないから全然わからないんですよ。だから妻には本当に助けられたなって感謝しています。いまもそうですけど、俺がサッカーに専念するためだけに環境を作ってくれていますから」
妻の加奈子さんからは、つねに謙虚であれと言われているそうだ。普段何か意見することはないが、節目節目で確信を突いてくる。大学生の頃から憲剛と二人三脚で歩んできたからこそ、その言葉には非常に重みがある。
「妻がいなかったらいまの自分はないですよ。『お前は何者でもないぞ、ちょっとサッカーができるだけだぞ』っていうようなことを、ちょうどいいタイミングで言ってくれる。サッカーのことはよくわからないけど、俺の調子だけはわかるらしいです。俺も意固地だから痛みを抱えていても無理してやるときもあるんだけど、言ってくるタイミングがいいから、『はい、じゃあちょっと休みます』みたいな感じで折れる感じ。だからこの14年間は俺1人の話じゃないんですよ。家族あっての自分です」
フロンターレでサッカー選手として成長し、父となり、子どもも生まれた。子どもたちの物心がつくまで現役でプレーしたいという夢を叶え、試合前に一緒にピッチに入場することもできた。いまでは等々力陸上競技場や麻生グラウンドは、子どもたちのちょっとした庭となっている。この時代にひとつのクラブで長年プレーできるサッカー選手はそうそういない。それゆえに中村憲剛という名前は本人の意思とは関係なくどんどん大きくなり、古参サポーターからはクラブの象徴として扱われるまでになった。
「自分では象徴だなんて思っていないですけど、周りの人たちに育てて大きくしてもらったのは事実です。きっとクラブとの相性がよくて、プロに入った時期とタイミングがばっちりだったんでしょうね。ただね、自分にとってもフロンターレって超越した存在なんですよ。所属しているクラブです、だけでは語れない。もはや人生の一部というか、切っても切れないものというか。J2からはじまって、優勝して、昇格して、優勝争いをして、代表に入って、ACLに出て、ワールドカップのピッチに立つこともできた。その間に結婚があって、妻の出産があって、大怪我もしました。で、2回目のワールドカップで落選して。もうね、すごく濃い人生だと思います」


憲剛の心の奥底には、大学2部リーグでサッカーをやっていた人間を拾ってもらったというフロンターレへの感謝の気持ちがある。だからこそ、クラブに対しての愛着は人一倍強い。
「何年か前に海外のクラブへの移籍話が出たときにまず頭に浮かんだのが、タイトルを獲らずに行っていいものかということでした。これがプロ入りして2、3年でチームがタイトルを獲っていたら、また違った選択をしていたかもしれないです。けど俺は入り方が違うというか、入れてもらってここまで大きくしてもらっているから、その恩返しをしたいという思いが強い。もちろん所属歴が長いというのもあるけど、それだけじゃない。他の選手とは思いが違う。それだけは間違いないです。いまはいい時代のフロンターレしか知らない人が多いけど、それはクラブの先輩たちが頑張ってくれたおかげなんです。苦しいときがあるからこそ思い入れが膨らむわけで、それを一緒になって乗り越えていくことで、どんどん愛着がわいてくる。それが思いの強さになるんじゃないかなって」
フロンターレは2005年にJ1に復帰してから2011年こそ11位という最終順位だったものの、それ以外では中位以上、2位3回と一定の成績を残している。しかし、ナビスコカップ準優勝2回を含めて(2000年に1度)J1でのタイトル獲得のチャンスがありながら、まだひとつも栄冠を手にしていない。憲剛が何度も口にする「あとはチームのタイトルだけ」という言葉は、選手やスタッフ、サポーター、クラブに関わる全員の思いが詰まっている。
「優勝争いができるチームを毎年作るのは難しい。だから若い選手もこの先10年チャンスがあるかどうかわからない。俺が24、5歳でフロンターレがぐっと上がってきているとき、これは絶対いけるって思ってました。でも、獲れていないのが現実です。ひょっとしたら俺のせいなんじゃないかって思うときもあったし、いまも思うところはあります。だからこそ、若い選手もつねにラストチャンスだと思って戦ってもらいたいんですよね」


昨シーズンのフロンターレは勢いに乗ったときに対戦相手を圧倒する一方で、自分たちのリズムを一度崩してしまうとなかなか立て直せず、そのままずるずるといってしまう傾向がより強かった。前に人数をかけた攻撃的スタイルなぶん、ひとつのパスで相手の間合いの逆を取れば大チャンス。だが、そこで相手ディフェンスに引っかかってしまえばピンチとなる。選手全員の技術レベルの高さはもちろんだが、選手1人ひとりの繊細さと大胆さといった意識の部分が揃って、はじめて成立するサッカーといってもいいだろう。
「うちはよくも悪くも自分たち主導のサッカーだから、どうしても調子の波がある。それを自分たちで感じ取らなきゃいけない。俺たちの目標は相手を崩し切って勝つことで、それが全試合でできれば優勝できる。だけどシーズンの中ではキーになる選手がいなかったり、連戦だったりと、いろいろな要素が絡んできますよね。だからときにはリーグ戦の34分の1と割り切って、苦しい展開を感じ取って我慢して守り勝つ試合もあるかもしれない。試合の流れはワンプレーでがらりと変わるし、この程度でいいやって妥協した瞬間、ゲーム展開は大きく変わる。そこを全員が自覚しなきゃいけない」
誰かがやるじゃなくて、自分がやる。自分がボールを取る、自分が突破する、自分が止める、そして自分が勝負を決める。その意思がうまくかみ合ったときに自分たちのサッカーになると話す。
「例えばユウ(小林悠)とかタサ(田坂祐介)なんかはその意思がプレーに表れるから、チームも引っ張られて自然と同じベクトルを向いたサッカーになる。そうするためにはタフじゃなきゃいけないし、自信も必要だと思います。ただ、若い選手がチーム全体のことを考えるのはそう簡単なことじゃない。そういう意味では去年リョウタ(大島僚太)やショウゴ(谷口彰悟)なんかがシーズンを通して中心として試合に出続けて、改めてチームのことを考える1年になったんじゃないですか。試合に絡んだ若い選手たちもいい経験をしたと思います。もちろん自分も試合に出ているから反省しなきゃいけないところもたくさんあるし、もっとチャレンジしていかなければいけないって感じていますけど」
そして、こう続けた。
「あとはやっぱり戦う気持ちと覚悟でしょう。うちの選手が持っていないわけじゃないけど、上位にくるチームには自分がやってやろうという選手しかいないじゃないですか。だからより強い気持ちを持たないと、相手を上回ることができないと思います。
それから、フロンターレのエンブレムを背負って絶対負けられないぞっていう気迫をどれだけ出せるか。本気になって戦える選手が何人いるかです。試合に出ている11人だけじゃ足りないし、誰かがやるだろうって思っている選手が1人でもいたら絶対に勝てない。
それが今年のスローガンの“チャレンジ・ザ・フューチャー”ですよ。偶然かもしれないけど、集大成という言葉をここで使っていないのってそういうことだと思うんですよね。ここから先の未来の話であって、20年を通過点にしようっていう年だと思う。だから元年にすればいいじゃないですか。タイトル元年にね」

フロンターレは優勝こそ逃しているが、J1在籍年数はすでに10年を超えた。観客動員数を含め総合的な視点に立って見れば、Jリーグ後発組としては成功している部類に入るだろう。しかし当の選手たち、現場の人間からすれば、つねにぎりぎりの勝負の世界で、サッカー人生をかけて戦っている。ときが過ぎるのはあっという間だ。悠長なことはいってられない。
「J1の他のビッグクラブと肩を並べたといってくれる人もいますけど、まだノンタイトルのクラブですから。だから優勝したら絶対変わると思うんです。こうすれば優勝できるって経験があれば次の世代に伝えられるんだけど、残念ながら俺が伝えられるのはサポーターや地域と一緒になってチームを高めてきた経験だけだから」
戦力や環境面といったチームの基盤はできあがってきた。そしてクラブの哲学となった攻撃的なサッカーで頂点に立ちたい。Jリーグの過去を振り返ってみると攻撃的なチームカラーで優勝を果たしたチームは数少ないが、それでも自分たちのスタイルを通して勝ちたい。憲剛はそう考えている。
「うちは昔から肉を切らせて骨を断つサッカーだけど、このスタイルで優勝したいんですよ。もちろん我慢しなきゃいけないときには割り切って戦うことも必要になってくると思います。ただ、その壁を突き抜けるまであとちょっとのところまできているのは間違いないんです。それはみんなが感じているんじゃないかな。そのための起爆剤が20周年という言葉になればいいんですけどね」
“チャレンジ・ザ・フューチャー”とは通過点。ここで完結するのではなく、ここが新しいスタート地点になる。今年も主将を務める憲剛の新たな戦いがはじまろうとしている。

「いま等々力に2万人のお客さんが来てくれているのは、面白い試合を見せてくれるって期待があるからだと思います。サッカー以外の面でも、いつも外から見ていますけどフロンパークの賑わいとかすごいですからね。スタジアム入る前から楽しくて、試合も楽しい。そして勝つ。そうなればベストです。自分たちのサッカーが成熟してきた。環境面も整ってきた。たくさんのサポーターがスタジアムに来てくれる。だから、もう手が届くところにきているんですよ。
あとは結果。すべては結果です。このサッカーで優勝してJリーグの流れを変えたいと思っていますけど、勝たなければただの負け犬の遠吠えというのもわかっています。けど結果だけを追い求めて中身がなかったら、それこそ未来はないでしょう。勝てなかったっていう結果だけを見て『ほら見たことか』『それだけじゃダメなんだよ』っていう人もいます。でも昔に比べて、いまは何もできなくて負けた試合はほぼないんですよ。それだけに本当に悔しいし、サポーターももどかしいと思います。
でもね、自分たちの信念は曲げたくない。このサッカーで優勝したら、きっと先につながっていきますよ。だから俺は成し遂げたい。今年も覚悟を持っていますし、チームのために全力を尽くして戦います。その覚悟を持った選手が若手からも出てくれるようになったら、それは本当に大きな力になるし、チームとして目指すところに行けると思います」
デビューしたての頃の憲剛は、本人が語るようにピッチではギラギラとした目で猛アピールし、練習以外では手当たり次第に先輩たちに声をかけ、プロの世界を生き抜いていくための術を学んだ。
そして現在──。もちろんあの頃の気持ちは忘れていないだろうが、いい意味で尖った部分が取れ、したたかに相手の嫌なところを突くプレーは円熟味を増している。
最後に、憲剛はこう話してくれた。
「優勝でしょ。優勝しかないよ。節目の年まで優勝の二文字を取っておいたんですって、みんなで笑って話せるような結果を残したい」



profile
[なかむら・けんご]
フロンターレひと筋14年目を迎えたチームの大黒柱。巧みなポジション取りで揺さぶりをかけながらボールを動かし、相手の急所を突く正確なパスでチャンスを演出する。2015年はリハビリからのスタートとなったが、シーズンが進むにつれて本領を発揮。チーム最年長選手だが、サッカーに対する情熱は衰え知らず。クラブとともに成長し、いまなお進化を続ける。
1980年10月31日、東京都
小平市生まれ
ニックネーム:ケンゴ