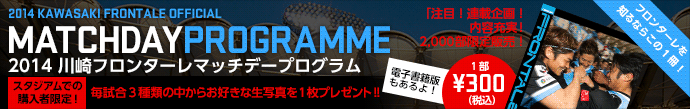Site Searchby Google Search
F-SPOTKAWASAKI FRONTALE FAN ZONE
狩野健太のプレーを見たことがあるあなたは、どんな印象を持っているだろう。
「うまい」「すごい技術だな」「ファンタジスタ」「天才」「目立つ」「金髪のうまい選手」…etc.
そんな風に思わなかっただろうか?

始まりは、些細なキッカケだった。
サッカー王国静岡県で生まれ育った狩野は、物心ついた頃からサッカーをしていたわけではなかった。野球をやっていた父親の影響で、野球もやっていたし、バスケもバレーも、本人いわく、「いろんなことをやりたいタイプ」で、スポーツに限らず、テレビゲームも何でも、とりあえず手を出してみた、という。
1993年、Jリーグが開幕した年に小学校1年生になった狩野は、地元の麻機サッカースポーツ少年団に入ることになる。Jリーグが開幕した、ということ以外にサッカーに対して特別な思い入れがあったわけではなかったし、最初は「いろんなことをやってみたい」という好奇心のひとつがサッカーに向けられた程度のことだった。たいていの場合は、その好奇心は長くは続かず、向いてないなと思ったり、飽きてしまうことが多かったが、サッカーだけは、飽きなかった。
「左足で蹴れたら、楽だろうな」
そう感じた狩野は、壁に向かって左足でボールを蹴り続けた。負けず嫌いだから、出来るようになるまで蹴り続けた。「練習をしよう」というような自意識はなく、ただただ、うまくなりたいという気持ちがボールを蹴らせていた。負けず嫌いな性分は、出来ないままで終わらせるという選択肢も生まなかった。
「誰かに言われたわけでもないし、うまくなりたいから自然とボールを蹴るっていう感覚でしたね。まぁでも、続いたのは、やっぱり楽しかったんでしょうね。結局、出来るまでやるっていうことは好きじゃなきゃやらないだろうし。うん、好きだったんでしょうね」
狙ったところにボールが当たるまで、ひたすら壁にボールを当て続けた。
中学は、静岡県の強豪・東海第一中に進んだ狩野。全国の中学生たちが最後の大会として臨む高円宮杯。年も押し迫った年末に行われるこの全国大会では、国立競技場で行われる決勝まで登りつめた東海第一中は、マリノスに0対3で敗れた。
「俺らの代は負けず嫌いが揃っていたし、それがいい方向に行ったと思う。全国の中学生の中で最後までサッカーやれたのはよかった」
その後、狩野は静岡学園に進み、「静学の10番」は周囲からの注目も期待も集める存在になった。1年のインターハイでチームが早々に敗退すると、井田監督から抜擢され試合に出るようになり、井田が掲げる静学スタイルの中で、自由に才能を伸ばしていった。
「独特なサッカーをやるチームだったし、やりたいことをやらせてもらい、思うように自分の感覚で攻撃させてもらいました」
振り返れば、ひたすらトラップ練習、止めて、蹴るを繰り返した小学生時代、当時は無自覚だったけれど、技術を身につける礎を作ってもらった。負けず嫌いだった狩野は「今は極端なことを言えば勝たなくてもいい」という方針だけは、しっくりこなかったと笑うが、個々の技術を伸ばそうと育ててもらったことに感謝している。
「小学校、中学、高校と、周りから、こうしろ、ああしろって言われた覚えがないんですよ。プレーに制限をされたこともない。そういうなかで自分で考えることも身についたと思います。それは今でもありがたかったと思いますね。だからお世話になった指導者の皆さんには、感謝しています」




ピッチに入れば、閃きと感覚で、無心でプレーしていたあの頃。
怖いものなしだったし、いつだって輝いていた。
実力も兼ね備え、高校時代から目立つ存在だった狩野は、ピッチに立てば「王様」のような存在だったのだと思う。
厳しい環境で、それなりに子どもの頃から練習を積み重ねてきた自負もあった。
それでも今、プロになって振り返ると思い出すのは、井田のこんな言葉だ。
「練習しろ」
目の前にいるのは「天才」「ファンタジスタ」と評される狩野健太だが、その口から出てきた言葉は、ギャップを感じる程シンプルなものだった。
「練習が大事なんだと思います」
「当時はもちろん練習をやっているなって思っていましたけど、今思えばもっとやっておけばよかったな、もっとやれることを見つけておけばよかったなと思います。井田さんには練習しろ、練習しろってずっと言われていました。要は思うようにボールを扱えるようになれ、もっと貪欲に突き詰めろってことだと思うんですけど、自分ではやっているつもりだったけど、もっとやっておけばまた違っていたのかなという後悔じゃないですけど、そういう気持ちはあります」
なぜ、そんな風に思うのだろうか──。
「この年になってみて、練習しかないんだなって改めて思いますし、井田さんが言っていたのはそういうことだったのかなぁって。たぶん、練習で身体に刷り込んで、それが自然と試合に出るんだと思います」
子どもの頃の狩野健太に、30歳の狩野がダブってみえる。うまくなりたい。その一心で「練習」とは意識せずに、ただひたすらに出来るまでボールを蹴っていた。それは結果的に、「練習」になっていた。プロになって、30歳になってもまた、サッカー選手として試合に臨むため、その過程にあるのは、いつだって日々の練習だ。
「結局、変わらないってことですかね。うまくなること。練習すること。大人になってそれが練習なんだと自覚しているだけで、やっていることは変わらない。練習しかないんだなって思います」


2003年、2004年と岡田武史率いる横浜F・マリノスはJリーグ2連覇を達成。日本代表選手も含め、錚々たるメンバーでJリーグを圧倒的な強さで席巻していた。狩野の元にはたくさんのJクラブからオファーが舞い込んだが、加入したのはそのマリノスだった。
「どうやって選んだらいいのかもわからなかったですけど、レベルの高いところで初めからやったほうがいいのかなと思って入りました。その結果、レベルが高すぎたんですけどね」と笑った。
キャンプに入った時は、自分の良さをアピールしようという心意気もあったし、がむしゃらにプレーして、決して技術面で劣ることはないということもわかった。ところが、プロとの違いを痛感するのは、間もないことだった。
「プロは技術とは違ったところでやらなければいけないことがたくさんある。判断、ディフェンス、すべてにおけるスピードが違いました。今思えばですけど、ああしなきゃいけない、ミスしちゃいけない、って考えるようになってしまって、それが最初の壁になりました」
一瞬の閃きや無意識で繰り出される魅惑とも言えるプレースタイルが武器だった狩野だったが、考えることによって、判断が遅れ、それによって、どうしよう、とまた考えて負のスパイラルにハマってしまう。結果、輝きが失われることになってしまった。
2005年は1試合、ほんのわずかな出場機会しか得られなかったが、それでも2年目以降はプロに慣れ、また周囲にも狩野のプレーの特徴を知ってもらい、徐々に出場機会を増やしていった。中澤佑二、奥大介、松田直樹、後にスペインから帰国した中村俊輔…、個性豊かな面々が集ったマリノスの選手たちの中で、勝利という目標に向かった時の熱量は肌で感じられる程、凄かったし、プロの鑑のような選手たちがたくさんいて、いろんなアプローチを身近で学ぶことができた。
「みんな、上手かったし、強かった。それぞれレベルが高いなかでいいプレーをしようとまとまった時は凄かったですね。とくに、佑二さんには可愛がってもらって、新幹線や飛行機でいつも隣だったし、サッカーの話を特別にするわけじゃなかったけど、身近で背中から学ぶことが大きかったです。あの人が満足しているところを見たことがなかったですし、プロとしての危機感みたいなものを常にもっていて、あのぐらいの選手がそういう意識でやっている、プロってそういうものなんだな、と」
やがて時は過ぎ、狩野健太のプロサッカー選手としての転機は、プロ4年目の2008年に訪れた。
その5ヶ月間を「地獄」だったと狩野は振り返る。
キャンプで負傷してしまった膝の内側靭帯を捻った際には、2ヵ月のリハビリを経験した。初めての大きな怪我と呼べるものだった。
ところが、ようやく出られた復帰戦で、第五中足骨を骨折してしまう。
診断結果を聞き、「全治3ヶ月
」と聞いた時、サッカー人生で味わったことのない辛さを知った。オペもすることになり、どん底に落ちた気持ちはなかなか晴れることがなかった。
だが、時間は流れていくものだし、なんとなく過ごしていても意味はない。大変ではあったが、もう一回気持ちを前向きに、復帰を目指すためのリハビリが続いた。
狩野健太が、2012年にマリノスを離れることになった時、多くのマリノスサポーターが2008年の狩野のことに思いを馳せた。それは怪我からの復帰という物語ではなく、復帰後、残留争いから救うことにもつながった狩野のプレーの眩さがあまりにも鮮烈な記憶として残っていたからだろう。
J1に残留するために決して負けられないジュビロ磐田との一戦で、山瀬功治が負傷で欠場、狩野はこの試合にスタメンで名前を連ねた。前節の神戸戦では後半途中から出場し、FKからオウンゴールを誘い引き分けに持ち込んでいた。そして磐田戦では、3-4-3システムの中で前で自由に攻撃を任され、ショートコーナーから「思い切って」貴重なゴールをアシストし、結果的に2007年天皇杯以来となるフル出場を果たした。
この試合前、狩野は、ある境地に達していた。
「ダメならダメでいいや。思いっきりやろう」
試合のことはあまり覚えていない。「無心」でプレーできたのは、いつ以来だったか−。試合後、ものすごくホッとした気持ちだったことだけは覚えている。
「自分が納得できるプレーが出来たのは、プロに入って初めてだったと思います」
当時は、なぜ納得いくプレーが出来たのか、その答えは自分でも見つかっていなかったかもしれない。でも、30歳になった今ならわかる。
「怖いものなしで、本当に思い切ってやっていた。周りからの見られ方も変わったし、プロでやれるんだって自信にもなりました」


ネルシーニョとの出会いは、プロ選手として大きな学びになる財産となった。
2013年から3年間、狩野健太は柏レイソルに所属。2013年、レイソルはネルシーニョの元でヤマザキナビスコカップ優勝も経験した。
監督だったネルシーニョは、“勝つための集団”であることに徹底的にこだわった。練習中に私語は禁止、「その会話は、勝つために必要か?」と問われれば、自ずと選手たちは答えを自分で見つけることができた。
「戦う集団、勝つために、ということで筋が通っていたから、選手は迷わずにプレーができました。レイソルにいた3年間のうち、細かい怪我も含めると半分は怪我やリハビリをしていましたが、ネルシーニョの元でプロとしての考え方を学べたことは大きかったですね」
2013年3月13日、日立柏サッカー場。3日前のFC東京戦でレイソルは0対3で敗れていた。狩野は初めてもらったチャンスで結果を出せず、背水の陣でこのACLに臨んでいた。
「FC東京戦は、周りにあわせなきゃ、とかうまくやろうと思ってしまって…。でも、セントラルコースト戦では、そういうことを一切考えていなかったです。何が何でもやろうと思った」
それが形になって表れたのが後半22分、中盤で崩したレイソルの攻撃の最後、狩野がジャンプして体勢を崩しながらもボールを左足で当ててゴールへと流し込んだのだった。輝きを放った瞬間だった。
2016年、フロンターレに加入した狩野健太は、新たなクラブでの挑戦にやりがいを感じていた。
「外から観ていた時と同じようにレベルが高い選手が多いし、いいサッカーをして勝つという風間さんのスタイルに自分もこだわってやらないとな、と感じました」
キャンプの時に、大久保嘉人から「周りを気にしなくていいから思い切ってやれ。どんどんシュートをしろ」と度々、声をかけられた。実際にキャンプ中、自分を出さなきゃいけないし、アピールして周りにわかってもらおうと思っていたので、思い切ってプレーができたという。
ところが、やはり試合が始まると勝ち負けの世界があるし、その中でチームにうまくハマらなければ、と考えてしまうようになった。そうなると、100%の狩野健太のプレーが影を潜めてしまう。それを乗り越えて、「やるしかない」という境地まで3月は少しずつ自分の心を近づけていった。
選手たちから受ける刺激もまた、狩野に新たなサッカー欲を与えるに十分だった。
「ケンゴさんは、こうやって攻めようとか、こういう動きをしたら相手がいやがるからこうしようなどと話をしてくれます。リョウタもああ見えて意外と意見を言うので、こういうときにはこうしてくれると助かります、とか話をしてきますね。いろんなタイプの人がいて、いろんな話をすることも刺激になっています」
狩野が理想とする選手像は、相手にとって嫌がられ、恐れられる存在であり続けること。うまいだけじゃなく、ゴールに絡んでチームに貢献して、この選手がいるとイヤだな、と思わせること。
「嘉人さんなんか、思い切りそうですよね。危機感を持たれるし、迫力が違う。でも、そういう嘉人さんが、あれだけ練習しているわけです。それにあの人こそ負けず嫌いの最たるものだと思うし、誰よりも点を獲りたいと嘉人さんは思っている。それがああさせているんだろうし、そこが半端なくすごい。そりゃ、あれだけ点取るわって納得します。そういう人が身近にいるのは本当に刺激になるし、自分も選手としてそこは負けちゃいけない、そういう気持ちを持っていなくちゃと思います」

2016年4月6日、ヤマザキナビスコカップ対新潟戦。
狩野の輝きを目の当たりにしたフロンターレサポーターは幸運だったと思う。
この試合も、狩野は、試合前にこんなことを考えていた。
「一番目立ってやろう」
自分の心を一番いい状態に持っていく、ということはとても難しいものだ。考えてしまったり、落ち込んだり、不安がよぎったり、といったマイナスのマインドをプラスに塗り替えて、「思い切ってやろう」と振り切った状態までもっていく。
考える作業をしてこなかったわけではないけれど、試合になれば自信を持って無心でやれていた「王様」だった学生時代、プロになって、壁にぶつかり、怪我をして、吹っ切って、輝きを放った数々の試合の出来事。自分が一番いい状態で100%を出し切るために、どういう状態にもっていけばよいのか、狩野も経験を繰り返してきたことで、その答えを掴むことができた。あとは、最高の自分に持っていくだけ──。
「そうですね、ようやくそれが分かってきたような気がします。自分のプレーを出すために、考えないで思い切ってやらなきゃなって。ピッチ外での生活や食事も大事だし、メンタルが特に大きい。この歳までわかるのに時間がかかりましたけど、ダメならダメでいい。この濃いチームメイトの中で一番目立ってやるっていう気持ちでやりたい。そういう気持ちがプロになってちょっと薄れちゃっていたと思うので、それぐらい目立ってやろうって今、思っています」
選手とクラブとそのサポーターと、出会いは一期一会であるがゆえに、自分自身を活かすための答えを見つけた狩野健太が、このタイミングでフロンターレに移籍してきたことの意味は、これからの結果で大きく変わっていくはずだ。
等々力で、狩野健太が眩いプレーをする姿をフロンターレのサポーターはこれから共有していくことだろう。
その魅惑のプレーに眼を奪われて心に焼き付けられたら、その瞬間はきっと、狩野健太自身も「無心」でサッカーが出来ている充実した瞬間なのだと思う。
そういう時間を1年でも1試合でも1分でも長く共有することができたなら、それは選手とサポーターにとって幸せな時間というより他ないだろう。
等々力が好きだ。と、狩野は言う。
マリノスもレイソルもフロンターレも、それぞれに特徴があって比べられるものではない。
今は、ここでゴールを決めたい。
チームに貢献したい。
「だから、等々力で点、獲りたいですね」
いろんな答えのパズルがはまって、残り1枚を手にしているような、そんなスッキリとした表情をしていた。
そのラストピースを、狩野自身がピタリとはめた時、等々力にどんな歓声が沸きあがるのか。
それを見てみたい。



profile
[かのう・けんた]
柏レイソルから完全移籍で加入したMF。中盤でタメを作りながらチーム全体のリズムを作り、抜群の攻撃センスで相手の予測の上を行く華麗な技を見せる。横浜FM、柏といった名門で磨きをかけたテクニックはすでに実証済み。年齢を重ねるごとに守備面での貢献度も増してきた。長いプロ生活の中で培ったキャリアをフロンターレでも生かしてもらいたい。
1986年5月2日、静岡県
静岡市生まれ
ニックネーム:ケンタ